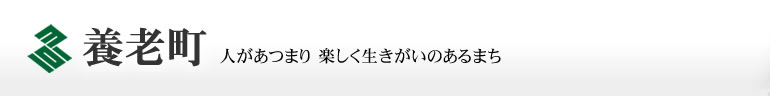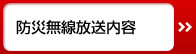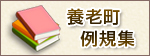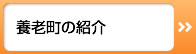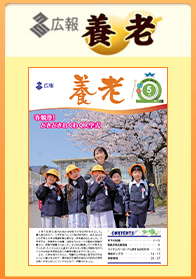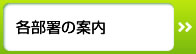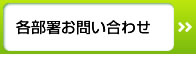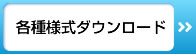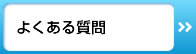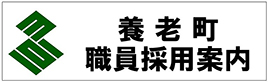公開日 2024年06月03日
養老町定額減税調整給付金について
給付金の概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、新たな経済に向けた「給付金・定額減税一体措置」が講じられ、これにより定額減税が実施されることとなりましたが、定額減税しきれないと見込まれる方に対し差額を調整し、給付します。
対象者等
令和6年1月1日時点で養老町に居住し、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円以下である場合に限ります。
定額減税については、以下のページをご覧ください。
給付額
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
算定方法
(1)所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数(国外居住者を除く)) - 令和6年分推計所得税額
= ア 所得税分控除不足額
※ア<0の場合は0
(2)個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額
= イ 個人住民税分控除不足額
※イ<0の場合は0
養老町定額減税調整給付金額
= ア + イ(1万円単位で切り上げ)
給付額にかかるパターン
配偶者、子1人を扶養している場合
ケース1 所得税額20万円、住民税額22万円の場合
納税義務者の減税可能額
所得税:3万円×3人=9万円
住民税:1万円×3人=3万円
※所得税額は令和5年分課税情報を基にした令和6年分推計値。住民税額は令和6年度賦課決定した所得割額。
給付額
所得税額20万円>減税可能額9万円、住民税額22万円>減税可能額3万円
推計所得税額、住民税額が減税可能額を上回るため、給付はありません。
ケース2 所得税額7万円、住民税額2.5万円
納税義務者の減税可能額
所得税:3万円×3人=9万円
住民税:1万円×3人=3万円
給付額
所得税額7万円<減税可能額9万円、住民税額2万5千円<減税可能額3万円
減税しきれないため、差額2万円(所得税分)+5千円(住民税分)=2万5千円を3万円に切り上げて給付します。
手続方法、支給開始日等
7月上旬より順次、対象者の方へ「支給確認書」をお送りしますので、必要事項を記入のうえご提出をお願いいたします。提出書類を確認後、支給させていただきます。
申請期限
令和6年10月31日(木)
※期限を過ぎると受給できませんので申請忘れにご注意ください。