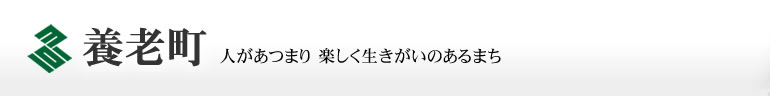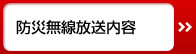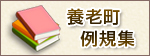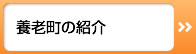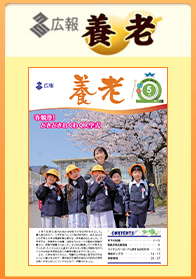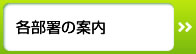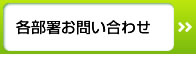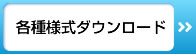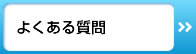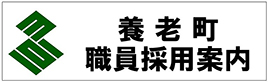公開日 2025年07月01日
介護保険料(第1号被保険者)のお知らせ
介護保険制度は3年ごとに事業計画を見直し、介護サービスの利用量や給付見込等を考慮のうえ、65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料を定めることになっています。養老町では令和6年3月に「第9期養老町介護保険事業計画・老人福祉計画(養老町シニアプラン21)」を策定し、第1号被保険者介護保険料の改定を行いました。
第9期(令和6~8年度)の65歳以上の保険料基準額(第5段階)は、
年額77,040円、月額6,420円となります。
今回の改定では、国が定めたきめ細かな所得段階の設定にあわせ被保険者の負担能力に応じ13段階の保険料を設定しています。
また、これまで同様、所得の低い人(第1~第3段階の人)に対しては保険料の軽減を行っています。
介護保険では、介護をみんなで支えるため、40歳以上の全ての人に保険料を納めていただくことになっています。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)については、加入している医療保険に、医療保険料と合わせて納めます。保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づいて決まります。
高齢化・長寿化が進みサービスの利用者が増加する中、安心して利用できる介護保険制度を将来に亘り維持していくため、保険料は必ず納めましょう。
65歳以上の介護保険料(令和6~8年度)
所得に応じた保険料の額
| 段階 | 対象者 |
令和6~8年度 (第9期) |
令和3~5年度 (第8期) |
||
| 第1 |
住民税 非課税世帯 |
生活保護受給者 老齢福祉年金受給者 課税年金収入額と年金以外の所得金額(※1※2)の合計が80.9万円以下 |
21,956円 | 22,464円 | |
| 第2 | 課税年金収入額と年金以外の所得金額(※1※2)の合計が80.9万円超120万円以下 | 37,364円 | 37,440円 | ||
| 第3 | 第1段階・第2段階対象者以外 | 52,772円 | 52,416円 | ||
| 第4 |
住民税 課税世帯で 本人が 住民税非課税 |
課税年金収入額と年金以外の所得金額(※1※2)の合計が80.9万円以下 | 69,336円 | 67,392円 | |
| 第5 | 第4段階対象者以外 | 77,040円 | 74,880円 | ||
| 第6 |
本人が 住民税課税 |
前年の合計所得金額(※2) | 120万円未満 | 92,448円 | 89,856円 |
| 第7 | 120万円以上210万円未満 | 100,152円 | 97,344円 | ||
| 第8 | 210万円以上320万円未満 | 115,560円 | 112,320円 | ||
| 第9 | 320万円以上420万円未満 | 130,968円 | 127,296円 | ||
| 第10 | 420万円以上520万円未満 | 146,376円 | |||
| 第11 | 520万円以上620万円未満 | 161,784円 | |||
| 第12 | 620万円以上720万円未満 | 177,192円 | |||
| 第13 | 720万円以上 | 184,896円 | |||
第1段階~第3段階の方の保険料については、負担軽減のため公費負担により軽減されます(表記の金額は軽減後の金額です)。
※1 年金以外の所得金額に給与所得が含まれる場合で、所得金額調整控除が適用される場合は給与所得額に所得金額調整控除額を加えた額から、所得金額調整控除が適用されない場合は給与所得から10万円を控除(控除前の額が10万円未満の場合は同金額を控除)します。
※2 所得金額の算出において、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除が適用される場合は、同控除後の額(控除後の額がマイナスの場合は0円)とします。
保険料の納め方
保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。
年金からの天引き(特別徴収)
老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円(月額1万5000円)以上の人
2か月ごと(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、支払いごとに、2か月分の保険料が天引きされます(老齢福祉年金については天引きの対象となりません)。
口座振替または納付書による金融機関への納付(普通徴収)
老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円(月額1万5000円)未満の人
年度の途中で65歳になられた人、または転入された人も普通徴収になります。
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
| 4/30 | 6/30 | 8/31 | 10/31 | 12/26 | 2月末日 | |
|
仮徴収 前年度2月と同一金額 |
本徴収 4~6期で年合計額から1~3期の納めた保険料を除いた額を振り分けます。ただし、100円未満の端数が生じる場合は4期にかかります。 |
|||||
※納期限が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限になります。