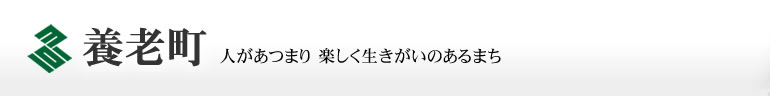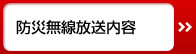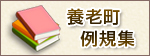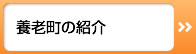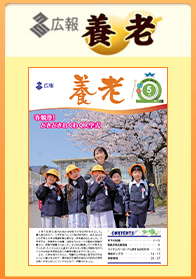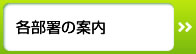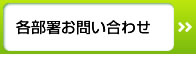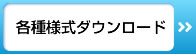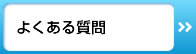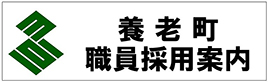■火を出さない
火を使う器具や施設は、ゆれで大きく移動したり倒れないように工夫しましょう。また、消火器やバケツを用意し日ごろから使い方を練習しておきましょう。
■家の内外をよく点検
家の中はいつも整理し、家具の安全な配置や、タンス・棚などの上に重い物やガラスケースなどを置かないようにし、転倒しやすい家具はしっかりと固定しましょう。
また、地域の危険個所など十分調べておいて確認しあいましょう。
■非常持出品の準備
いざというときにあわてなくてもよいように、非常時の持出品をふだんから準備して、一カ所にまとめておきましょう。新しく取り替えることも忘れずに。
■家族みんなで話し合い
いざというときに、おちついて行動ができるよう日ごろから家族みんなで話し合いましょう。地震が起きたとき、誰が何をするか決めておきましょう。また、避難経路や避難場所、家族間の連絡方法などを確かめましょう。 |
■災害伝言ダイヤル「171」
|
いざと言うときには、災害用伝言ダイヤルセンターを開設し、家族の安否・避難先などを録音(伝言の録音)したり、大災害などで電話が混んでいる時でも安否伝言を聞く(伝言の再生)ことができます。
| ■伝言を録音する方法■ |
■伝言を再生する方法■ |
|
|
|
| ↓(ガイダンスがながれる) |
↓(ガイダンスがながれる) |
|
|
|
| ↓(ガイダンスがながれる) |
↓(ガイダンスがながれる) |
|
|
|
・伝言蓄積数には限りがあります。(1つの電話番号に3~7伝言)
・録音時間は1伝言30秒以内
・伝言は伝言してから48時間預けることができます。
・「171」は、一般電話、公衆電話、携帯電話、PHSからも利用できます。
・海外からは使用できません。
・利用する場合は通話料金がかかります。
指定緊急避難場所
災害が発生した時又は発生しそうな時に危険から命を守るために避難する場所として、町が指定するものです。
地震、洪水、土砂災害等の災害の種類毎に指定しています。
指定避難所
避難した方が、災害の危険性がなくなるまでの一定期間滞在する施設として、町が指定するものです。
指定緊急避難場所のうち、小中学校、地区公民館、体育館などの屋内施設を指定しています。
指定避難所・指定緊急避難場所一覧.pdf(250KB)
※避難上の注意事項
・緊急避難場所への避難が命を守るための行動として、常に正しいとは限りません。屋内の安全な場所での待避や、近隣の建物へ移動した方が安全な場合もあります。その時の状況に応じて行動しましょう。
・安全に避難できる緊急避難場所はどこか、あらかじめ確認しておきましょう。
・緊急避難場所へ移動する際には、徒歩で安全な経路を確認しながら、なるべく地域の人たちと一緒に行動しましょう。
・滞在時間が長くなることを想定し、可能な限り食糧・飲料水・日用品・救急薬品などを持参しましょう。
|
■防災行政無線
防災行政無線は、災害発生が予測される場合や災害発生時には、迅速かつ的確な情報を町民のみなさんに伝達する緊急の通信施設です。
この施設は、町役場無線室の親局から、町内36カ所の屋外拡声子局と各公共施設をはじめ各地区防災隊長や消防団幹部宅などの戸別受信機に一斉放送されます。
|
|
|
■町の防災対策と自主防災隊
警報が発令されると、町関係職員は警戒体制をとります。大きな災害が予想されるときや発生した場合はただちに町役場内に(災害対策本部)を設置し、防災無線などを利用して、災害(被害)情報の収集・伝達、災害復旧などにあたります。また、地域で迅速・的確な防災活動をしていただくため、自主防災隊が編成されています。地域ぐるみで助け合いながら、消火活動やけが人の救出、避難誘導にあたりましょう。いざというときのために、ふだんから防災訓練などに積極的に参加しておきましょう。
|
■地震のときの心得10ヵ条
-
グラッときたら火の始末
「火を消せ」と声を出し、とっさに行動。小さな地震でも、火を消す習慣。
-
テーブルなどの下に身を守る
大型家具から離れる。子供を守る。
-
戸を開けてまず出口の確保
とっさに玄関のドアを開け放つ。
-
あわてて外に飛び出さない
あわてて外に飛び出すと瓦や窓ガラスが落ちてきてたいへん危険。
-
火が出たらすばやく消火
近所に大声で知らせながら消火活動。
-
わが家の安全隣の安全
声をかけあって火の用心と助け合い。
-
門や塀には近づかない
地震の震動で倒れやすいものには決して身を寄せない。
-
室内ではガラスの破片に気をつける
スリッパをいつも手近に用意する。
-
危険をさけてすばやく避難
ぐずぐずしないで安全な場所へ。
-
正しい情報を
ラジオのニュースなどを通じ正しい情報をつかんでおちついて行動をする。
■非常持出品 これだけは用意しておこう
| 非常食・水 |
カンパンなど火を通さなくても食べられるもの。水はミネラルウォーターなど。赤ちゃんがいる場合は粉ミルクなども。 |
| 懐中電灯・ろうそく |
停電時や夜間の移動に欠かせない。予備の電池も忘れずに。
ろうそくは、太くて安定したものを。 |
| 携帯ラジオ |
デマにまどわされないように正しい情報を得るため。小型で軽く、FMとAMの両方聴けるもの。予備の電池も忘れずに。 |
| ヘルメット(防災ずきん) |
屋根瓦や看板などの落下物から頭部を守るため。避難路は転倒事故も多いので必ず用意を。 |
| 衣類 |
下着、上着、手袋、靴下、ハンカチ、タオルなど。赤ちゃんがいる場合は紙おむつなども。 |
| 生活用品 |
ライター(マッチ)、ナイフ、缶切り、ティッシュ、ビニール袋など。赤ちゃんがいる場合は哺乳びんなども。 |
| 救急薬品・常備薬 |
ばんそうこう、ガーゼ、包帯、三角巾、消毒薬、解熱剤、胃腸薬、かぜ薬、鎮痛剤、目薬、とげ抜きなど。 |
| 通帳類・証書類・印鑑 |
預貯金通帳、健康保険証、印鑑など。住所録のコピーもあると便利。 |
| 現金 |
紙幣だけでなく、公衆電話用の10円硬貨も用意したい。 |
|
| 非常食 |
そのまま食べられるか、簡単な調理で食べられるもの。アルファ米やレトルトのごはん、保存のきくパン(缶詰も市販されている)缶詰やレトルトのおかず、インスタントラーメン、切りもち、チョコレート、氷砂糖、梅干し、チーズ、調味料など。定期的に期限を確認し、古いものから食べて、いつも新鮮なものを補充しておく。 |
| 水 |
飲料水は1人1日3Lが目安、ミネラルウォーターの保存期間は、ペットボトルで2年、缶で3~5年程度(冷暗所に置いた場合)。随時、保存期間の確認を。さらに、生活用水の確保も忘れずに。風呂の水は次に入るまで抜かずにフタをして、寝る前はいつもポットややかんに水を入れておく。 |
| 生活用品 |
燃料は短期間なら卓上コンロや固形燃料で十分。ガスボンベも多めに用意を。その他、洗面具、生理用品、ビニール袋、新聞紙、ビニールシートなど。 |
|
■非常持出品の用意のポイント
あまり重すぎると避難行動に支障がでるので、あまり欲ばりすぎないことが大切です。重さの目安は男性で15kg、女性で10kg程度。できれば各自にひとつずつ背負いやすいリュックを用意しそれぞれの持ち出しやすい場所に保管しましょう。